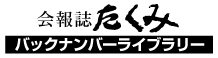定例研修会報告 令和6年度
![]()
令和6年度 第6回研修会
「松代旧横田家」見学・お花見・ 陶芸教室
開催日/令和7年4月12日
講/師/白石 大陸氏(サンコー特機㈱ 営業課長)
4月の研修会は、毎年恒例となっている松代での見学会・ 花見・陶芸教室を行った。
午前中は松代旧横田家を見学した。
旧横田家は昨年度に改修工事を行い、その際に防火設備工事を担当したサンコー特機の白石氏より解説をしていただいた。
主屋の茅葺屋根を守る放水銃は、火災時には自動で高粘 度液体が放水されるとのこと。
高粘度の液体は屋根表面に付着することで、その後の飛び火による着火を防ぎ、かつ内部への空気の流入を遮断し、火の入り込みも防ぐとのこと。
伝統的建造物を火災から守るための技術の進化を学ぶことができ、大変有意義な研修となった。
昼食は、雲ひとつない好天かつ満開の桜の下で、花見弁当をいただきながら和やかなひと時を過ごした。
午後は、松代焼の松代陶苑に移動し、各々1kgの粘土をもとに約2時間、茶碗、湯のみ、お皿等、個性豊かな作品作りに各々集中して制作をした。
総会の会場で、松代焼の独特の風合いに焼きあがった作品が展示されるのが楽しみである。
![]()
令和6年度 第5回研修会
リレートークVol.29
「伝統工法 石場建ての家を学ぶ」
開催日/令和7年2月26日
講/師/小坂 浩一氏(小坂建設㈱ 代表取締役)
/// 柳澤 崇成氏(小坂建設㈱ 大工)
令和6年度第5回研修会は2月26 日、 長野市柳原交流センターで、小坂建設(長野市)社長の小坂浩一 氏を講師に、小坂氏が 茨城県牛久市で手掛 けた「伝統工法石場 建ての家」について学んだ。
昨年5月に完成した木造平屋建て、延べ84.69 ㎡の住宅 で、採用した石場建て工法は、建築基準法で仕様が規定されて いないことから、確認申請にあたっては限界耐力計算による構造適合性判定の申請を、小坂氏が自ら計算して行ったことを報告した。
耐力壁には地震に強い板倉造りを採用したという。小坂氏によると、使用した木材については長野市内の工場で加工し、現地で組むだけとしたが、関東は建物を強固にする傾向があり、許可がなかなか下りず、検査に時間がかかったと説明。
二重 屋根の作業は5月の梅雨時期に重なったため、雨の侵入に特に気を付けたことや、落とし込み壁の作業では「足場が邪魔になって大変だった」といった苦労を写真をもと に紹介。
伝統工法に対する氏の思いに、参加者は熱心に耳 を傾けていた。
![]()
令和6年度 第4回研修会
リレートークVol.28
「塗装のいろは・適材適所の塗装術」
開催日/令和6年12月11日
講/師/五明 良平氏(㈱五明 代表取締役会長)
/// 宮原 博一氏(㈱五明 営業部長)
/// 森田 哲平氏(菊水化学工業㈱ 建材塗材事業部 松本営業所 所長)
長野市柳原交流センター大教室にて、(株)五明より代表取 締取締役の五明氏、宮原氏、菊水化学工業(株)の森田氏から、建築の長寿命化やリフォーム・リノベーションの需要が増える中で、改めて塗装の「いろは」や 適材適所の塗装につ いて紹介・講義をしていただいた。
五明会長より、塗装の歴史の大きな流れ、塗装材の概要をお話しいただいた。
菊水化学工業の森田氏からは、塗装の歴史と変遷、塗装の三つの役割(保護・美観・機能性)や、建築物の用途・歴史による塗 料の変化の過程を学んだ。
塗装の種類については、塗料の種類により耐用年数や硬さ・樹脂の分類をイラストや写真を用いて、わかりやすく解説していただいた。
最後に平成から令和の塗料として、遮熱・断熱効果のある有機・無機ハイブリッド上塗料についての講義をしていただいた。
有機・無機ハイブリッド上塗料の実演では、塗料を塗った鉄板を熱し、会員が触れ、実際の塗料の遮熱・断熱効果を体験した。
会員からは有機・無機ハイブリッド上塗料の施工性や省エネ効果などについて積極的に質問があがり、実務に直結する有意義な研修会となった。
![]()
令和6年度 第3回研修会
OYAKI FARM いろは堂 見学会
開催日/令和6年11月16日
講/師/遠野 未来氏(遠野未来建築事務)
令和6年度第3回研修会は11月16日、長野市篠ノ井にある「OYAKI FARM」で開き、設計を担当した遠野未来氏(遠 野未来建築事務所代表)の説明を聞いた。
遠野氏は、設計趣旨や建設に至る背景を紹介し、参加者らは建物の空間構成や構造、自然素材や伝統技術にこだわった意匠などを各々見学した。
遠野氏によると、建設地一帯には約1万年前から人間が住 み着き、縄文時代から弥生時代にかけて集落があったという。建設地のそうした背景 を踏まえ、この建物では、「土から生まれ大地に還る」「自然と一体となる生命力 のある」建築を目指したと紹介した。
敷地全体を取り巻く円と、建物の円とで全体を構成している。
建物は、HACCP対応の工場部分が面積の8割超を占め、それ以外は、おやきの直売所とカフェを備えた建物となっている。
北側 は太鼓柱によるガラスのカーテンウォールとし、その真ん中にあたる正面には建設残土を使った版築壁のエントランスが建物を印象深いものにしている。
遠野氏は「木と一緒に土も木造建築に多用していきたい」と 話す。その「木造」に関しては、構造材に根羽村産のスギを使い、登り梁にはヒノキを使った。手刻みによる木組みが建物 全体を特徴づけている。
2階のテラスは「都市の中の余白」として一般に開かれた公共スペースとして位置付けており、参加者らは、見学後、テ ラスで昼食を取り、遠野氏を囲んでさまざま質問を投げかけていた。
![]()
令和6年度 第2回研修会
松本の奥座敷「浅間温泉の 歴史を巡る」
開催日/令和6年9月21日
講/師/藤松 幹雄氏(藤松建築設計事務所)
/// 小宮山 吉登氏(㈱倉橋建築計画事務所)
/// 川上 恵一氏(㈱かわかみ建築設計室)
令和6年度の第2回研修会は、藤松幹雄氏、小宮山吉登氏、川上恵一氏の3名を講師に迎えた。
講師から松本市浅 間温泉の歴史について学び、地域内の建物を見て回った。
はじめに本郷公民館に集合し、講師たちから浅間温泉の歴史やまちづくりを聞いた。
藤松氏は、浅間温泉が縄文時代から存在する歴史的な場所であることを強調し、 明治時代以降の発展過程を説明。
片倉製糸の開業に伴う近代化や、旅館業の発展・建築様式の変化について解説した。
スポット巡りでは、1919年の建築で近代和風建築に分類される「松門文庫」を見学した。
建物は、和洋折衷の意匠を持つ木造2階建て、寄棟桟瓦葺きの建築。
外壁は漆喰を基本に傷みやすい部分にモルタルを用い、窓周りや玄関ポーチのペディメントの装飾、ポーチ柱の研ぎ出し仕上げなどが特徴であるほか、ポーチ屋根は銅板の鱗葺きで松本市内では希少だという。
松門文庫の見学後 は、中浅間駅停留場「チ ンチン電車」跡地、降旗 邸、目の湯、梅の湯、松 本十帖・小柳、松本十帖 「おやき」・検番などを 見て回った。
![]()
令和6年度 第1回研修会
「軽井沢A邸別荘」見学会
開催日/令和6年7月27日
講/師/高橋 志行氏(㈱むね工房 代表取締役社長)
/// 坂田 守夫氏(㈱坂田工業 代表取締役会長 )
当会会員むね工房の高 橋氏が木工事を行い、屋根防水を当会専務理事の坂田工業・坂田氏が担当した、軽井沢で7月に竣工を迎える「軽井沢A邸別荘」を竣工直前のタイミングで見学した。
設計はand to建築設計事務所、施工は北野建設。 新築の別荘はプライバシーの観点で見学する機会が少なく、大変貴重な機会となった。
軽井沢駅北側の閑静な別荘地の森の中に、一見、奇抜なデザインの建物が現れた。緩やかに丸みを帯びた軒先、光を落とす中庭、開放的なテラス、建物全体を支える丸太の列柱が、目を引きながらも、自然の中に溶け込んだ、既成概念に縛られない 魅力ある建物であった。
構造は、木と鉄のハイブリッド構造。屋根の登り梁は1本1本形状が異なるため、プレカットとしており、登り梁同士は、屋根内で鉄骨の吊り材で支えることにより、曲線を用いた大変複雑な形状を実現している。 また、柱脚は鉄骨の無垢材、 柱は杉の丸太材を使用している、と高橋氏が説明。
まっすぐスラブを貫き屋根を支える列柱は、森を連想させるような神秘的な空間を表現していた。
仕上げとしては、屋根と外壁は同様のアスファルトシングルき、屋根は緩勾配のため、仕上げの下に全面防水としている、と坂田氏から説明があった。
また、2階は、既存樹木を生かした計画となっている。
内部空間は中庭に面して、ダイニング、リビング、テラスが 放的につながっている。既存樹木を生かした中庭は大変魅力的であり、土地の自然を最大限に活かしつつ、内部に取り込むた めの、工夫を感じられた。