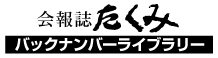![]()
旭日双光章(25年春の叙勲)の出澤潔さん語る
○木造技術の継承は危機的状況
○技能者への先入観の払拭
![]()
数年前、建築士会連合会の会報のオピニオン(3回連続)で、木造技術の継承、建築士の制度などについて書いた。「長野県の2006年の木造建築、大工工事業の事業所は2001年より620カ所減少し、3941カ所。従業員数は3352人減。平均年齢は54歳で、2.6歳上昇。プレカット率が9割になっている」。
こうした現状を見た時、いい住まいを提供するための技術はどう守られていくんだろうか、どう伝えられていくのかということを、考えなくちゃいけない。
建築も市場経済の行為と考えた時に、これを否定するわけにいかない。そういった中で、これをもっと前向きな議論に発展させようというのが連合会への提案だった。
![]()
つい先月号の連合会の会報に、こんな資料がある。「(建設業の)新規入職者数が減り、絶対的に数が減少。就業者数が3割近く減少。高齢化が大幅に進み、若手が大きく不足。年々高齢化が進行し、直近では55歳以上が3割、29歳以下が1割。
これは建設業全体の数字で、いわゆる技能者、職人と呼ばれる人に限ればもっと高齢化が進んでいると考えられる。非常に危機的な状況にある」。
![]()
延べ面積が30坪の2階建て、一部に無垢材を表した高気密高断熱の住宅の建て方の完了から竣工まで、大工さんがどんな仕事をしてるか調査した結果がある。すると、寸法取り、石膏ボードを切る、ビス打ち、それが大工さんの技術の大半だという。そう考えたとき、大工さんの技術というのはどうなんだと肌寒くなる。
名匠会とはまったく違う話だが、世の中にはそういう話があって、そこから目をそむけることはできないし、じゃあどうしたらいいかという問題がある。
技能者の仕事や求められる技能の中味は変りつつある。技能者に対する従来の先入観を払拭することが、この産業の未来像を描く事になる。建築が資本主義、市場主義の中での住宅産業という側面がもっと強くなる事を考えると現状を否定するわけにいかない。そう考えた時、街で働く技能者、職人さんが、ものをつくって人に喜んでもらうことを体感し自覚することがどうしても必要で、その上で自分の生活を守ってもらう、ということが必要。
これから住宅がどういう方向へ進むかわからないが、住まいには数値で計れない大切な価値があり、つくる人もつくることで人に喜んでもらう、そうした気持ちが、みんなの気持ちの中に入っていくと、いまの住まいよりは、もう少しいい住まいができていくのではないだろうか。
○宮本先生の存在に背中を押され
![]()
こっちへ戻ってくる時、非常に不安だった。田舎に戻ってきて仕事ができるのかできないのか。(そのころ)たまたま神田の本屋に行ったら、こういう本があった(雑誌「近代建築9」を掲げながら)。それをペラペラっと見てたら、宮本先生の特集があった。こんな特集を組むようなことをやれる人がいるんだから、「オレも何とかやれるのかな」と、すごく力付けられた。この本を大事にとっておいてある。いただいた手紙も大事にとってある。それから宮本先生が新聞に載ったりしたのも全部とっておいてある。
私にとってはとても大切な宝物。