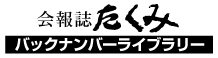![]()
平成23年度通常総会 記念講演会「歴史から学ぶ」
◆民を治める「やさしさ」
小学生の頃、郷土史の先生は言っていました。
いまの小布施の半分、都住という地域になりますが、そこは元々都住村といって、天領ではなくて、新潟の椎谷藩という柏崎あたりの、たった一万石の大名の土地でした。
お城も屋敷もない大名で、かわいそうなことに領地の半分の五千石が小布施周辺です。
収入の半分が小布施周辺ですから代官屋敷もありました。
でも、この代官屋敷を小布施は郷土史として小学校の生徒に教えるのですが、小さい代官屋敷で、もちろん現在は建物も敷地も分からなくなっていますが、図面があって、小さい三部屋くらいしかない代官屋敷です。
その代官屋敷に本当の侍は一人、あと二人は戦となれば一応、刀を支給されて、足軽として戦うという程度。普段はもちろん刀なんて持っていません。もう一人、男ですが、女中さんの代わりみたいな賄いがいました。
だから、先生は「代官とはいっても権力がない。百姓一揆があったら、真っ先に殺されるのが奉行所なんだよ」と言っていました。軍事力がありませんから。「江戸時代の侍というのは、武力で民を、というのはありえない」としっかり言ってました。
同様の趣旨のことを、井出孫六さんという物書きが30年くらい前に言ってます。
それは秩父困民党の乱を題材にした小説を書いていたときで、井出さんが調べて驚いたことに、秩父山中の民衆は、いわゆる鳥や獣を撃つために火縄銃を三千丁以上持っていたということです。
秩父だけで江戸城にある全鉄砲よりもたくさん持っていた。これが、関八州だったら万を超える鉄砲があるだろうと。
そうすると、日本という国は民衆がその気になればいつでもクーデターを起こせるような、そういう国だったということです。そうしてみると、徳川幕府というのは、一体、何をもって民を治めていたかということです。
それは、いわゆる生き方とか行いの美しさであり、お行儀の良さであり、そうした美学で抑えていたというのが実態に近いのかもしれないと言っています。
これは世界史的にもすごいことで、大したものです。
諸外国の常識なら何回もクーデターが起こっています。
民を治めるやさしさの一つの証明は至る所にあります。
東京に浜離宮というのがあって、池があります。この池の水は真水ではありません。海の水を池に使っています。だから鯉を飼おうにも飼うことができません。世界の権力者にこんな権力者がいるでしょうか。
世界の常識からすれば、何々が貴重だったら、その貴重なものこそ湯水のように使うのが権力者です。
江戸の町というのは常に水が不足している町でしたから、玉川上水とか神田上水とか、多摩川の方から木樋で水を運んできていました。八っつぁん、熊さんにはよく井戸が出てくるけれど、あれは井戸ではなくて、下に木樋が通っていて水路に通しているだけです。それほど水の足りない江戸の町ですから、徳川幕府は、海の近くで、しかもやっぱり海辺に面した浜離宮のようなところでは、真水ではなく、やっぱり海水で賄おうと、こういう節操がありました。
権力者特有の感じがありません。大変、気を遣った統治をしているわけです。ですから、「統治」という言葉が語感として合うかどうか。非常に気を遣って治めてきました。
ですから、民主主義とか制度はなかったかもしれませんが、民百姓の意を汲んだという点では、日本の為政者というのは極めて注意深いし、民百姓のサイドに立った行政を行ってきたと言えます。それに比べると、いまの為政者はお粗末過ぎではないかと思うわけです。
そうした行政のやさしさは、たとえば罪人のための職業訓練所のようなものをつくるとか、いろいろなことをやっていますが、世界に冠たるものは、やはり御殿山でしょう。
御殿山というのは、参勤交代で来た島津とか西国の大大名を迎えるために、将軍が品川の上の山に造った御殿で、そのために「御殿山」と言われました。
それがやがて、そんな儀式は止めようということになり、御殿もいらないということになって、御殿を壊し、桜の名所にしました。町民に一般公開したわけです。
ですから、江戸の浮世絵を見ると、板橋にある飛鳥山とそれから御殿山が二大桜の名所で、後に中野とかいろいろなところに桜の名所が出来てきますが、一般の人間に公園として提供したのは、おそらく世界でも最初です。
ですから、日本の歴史で本当に誇るべきは、権力者も一般の民百姓のことを考えていたし、それから民百姓も自分たちの生活のある部分を公のために尽くすという、その両方があったということで、特筆すべきことだという感じがあるわけです。
◆所有権の弱い森や林
そうして、もう一つの工夫として、土地の所有権が文献では分からないのですが、私の感じでは二種類あったと考えています。
一つは宅地と田畑、この所有権は所有者の権利が強いという点で、いまの所有権とほとんど同じ。
ところが、平地も含めた林や森、これについては持ち主の権利は非常に弱い。
水路や馬入れ道ほどではないにしても、周辺のコミュニティで共有する、所有者の自由にならない共有的な部分があるわけです。
したがって、芝草刈りやキノコ、山菜。それらは周辺の持ち主でない人たちも出入りしていいと。多分、色々やらなければいけないことはあるけれども、出入りは自由ですから、当然、塀なんかは建ててはいけない。森や林については、自分のものだからと自由にしてはいけない。森や林として使うから所有権を認められるという、そういう権利です。
これがどうやら連綿と生きてきた。
ところが、私は法律学者が一番いけないと思うのですが、そういう日本の慣例、歴史を勉強しないで、日本は成文法主義ですと決めてしまった。戦後まもなくですが、法律ですべてを規定するフランスの真似みたないことをやったわけです。
ところが、日本は元々イギリスのように慣習法の国です。それをそういうことをやったものですから、おかしくなってしまった。
首都圏を中心に住宅が不足しているからと、ババッと、あっという間に武蔵野の雑木林を伐ってしまった。土木技術が発達してくるからブルドーザーなども登場します。そうして、山も崩して宅地にしてしまった。
江戸時代から連綿と生きてきた慣習法である土地の所有権。林や森は、林や森として使っている限りにおいて所有権が認められ、しかし、たとえ所有者のものであっても、ほかの使用目的には使ってはいけないという不文律が、1945年以降、どんどん破られていくわけです。