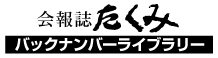![]()
平成23年度通常総会 記念講演会「歴史から学ぶ」
◆合理的な隣家との関係
いまの家を見ると、隣の家、自分の家、それぞれお互いに塀を作っている。ナンセンスです。
江戸時代までの作法ではそういうことはしませんでした。
塀を造っても自分の家か隣の家、どちらかが造る。隣の家が建てたなら、自分の家側は自分の家の塀として使わせてもらう。
通りに対しては、かなりセキュリティを考慮していて、屋根から泥棒が入ってこないよう、見せかけかも知れませんが、鉄や竹や木など尖ったものを付けて防いでいます。
また、隣の家とは通路を付けているのが普通です。これが本当の意味でのセキュリティです。
いまのように四方をすべて厳重に囲ってしまうと、何かあったときに逃げられません。
江戸時代までの作法では、急な場合に隣の家が逃げ場所になりました。そこには逃げるための木戸を必ず設けるし、高い塀や高い建物で厳重に囲うのは表通りに対してだけでした。
そういうことも実際上の機能として、自然な形で防犯面のことを考えています。
隣や裏のお宅とは、通りに面してはそれぞれ塞いでいるけど、中の庭は共通、使う庭になっているというケースもある。なかなか知恵のあるやり方をしていると思うわけです。
◆公の担い手
そして、やっぱり大事なのは、公の担い手というのは、一般の人間だという考え方です。
その証拠に、私の手元に文久とか慶応といった幕末の小布施、小布施といっても本当に狭い範囲ですが、名主の選挙の委嘱状みたいなものがあります。
「貴殿は今回の入れ札の結果、落札したので、名主を務めてほしい」というものです。
小前一同という形で、ずらずらと名前が書いてあるのですけど、公文書ですから朱印は使わずみんな黒印ですが、感心してしまうのは、どれもいまの私の実印よりも彫りが細かい実印を使っています。そして重要なのは、学校の歴史と違って5人に1人ぐらい、女の名前が出てくるのです。菊とか松とか。これは何を表しているのかといいますと、多分、名主の選挙ですから、一人一票じゃなくて、一家に一票です。一家に一票で、女の名前があるということは戸主が女ということです。
これは非常に重要なことで、我々、高校や中学の歴史では、そういう風には習わなかったですね。女なんか人間扱いではないといった感じでした。
おかしいなと思って考えたら、こういうことです。明治時代になって、戸籍法ができたときに、良くも悪くも侍の価値観、生活を一つの法律に取り込んだ。侍は、戦争があったときに兵士として出撃する約束で禄を食んでいます。ですから、女が戸主というのはまずいわけです。
女は兵士として行けないから侍の家は1歳でも男の子が戸主で、そういう建前になっている。
ところが、それは7%の人で、侍以外の93%のところは、そんな馬鹿なことは言っていられない。
亭主が若いうちに死んでしまえば、自主的にその一家の差配をするのは未亡人です。したがって、名主の選挙のときにもちゃんと女が一票を投票しているということです。
私たちは「水呑百姓」という語を習いました。学校の先生からは年貢で米を取られてしまい、水くらいしか飲めないから水呑百姓だと、こういう風に教わりました。
網野善彦さんという歴史学者が30年ぐらい前に能登の方をいろいろ調べていたとき、それはウソだということが分かったのです。
水呑とはどういう意味かというと、税金を払わないということ。税金を払わないというのは、田や畑を持っていないということです。これが水呑の意味です。
能登の輪島に行くと、水呑である富豪というのがいっぱいいます。
塗り物屋の問屋とかそういう人たちは、農地を持っていませんが大富豪です。
水呑の大金持ちというのが出てきて、網野さんは困ってしまった。どういうことかと調べたら、結局、水呑というのは、課税対象の資産を持たない、ということでした。
当時、商人はお金があると田畑を買い、場合によっては開発もやっていました。開発地主というのも多いのですけど、そうして大地主になるわけです。
しかし、輪島のようなところは農地の面積が元々取れないところですから、貿易が中心です。
北前船貿易で儲けたとか、あるいは漆の問屋だとか、そういう人たちはお金はあるけれど、田畑を買うような無謀なことはしません。
田畑を持たないから税金を払わない。税金を払わない人間を水呑といったわけです。
よく、間口が狭くて奥行きが長い町屋を、税金が間口によって決められたから、できるだけ間口を狭くしているといって説明されますけど、半分本当で、半分ウソです。
あれは税金ではなく、共益費です。町内を運営していくのに、お上じゃなくて、いまでいう共益費みたいなものが必要となる。この共益費は間口に比例するというわけです。
厳密な意味では税金ではないです。
これも間違いの元なので、訂正しとかなくてはいけないと思います。
日本の歴史学者は真面目すぎて、文献にないことは一切ない、としてしまう。そして、実状に合わない歴史観が作られていく。しかも、戦後のように、左翼マルクス主義系の影響を受けると、全部「搾取」という問題で捉えられてしまう。