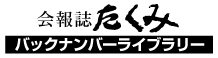![]()
平成23年度通常総会 記念講演会「歴史から学ぶ」
◆居心地の良い外部空間
そして、これらを具体化するにはどうしたらいいかということを考えました。
建物が豪華だろうが粗末だろうが、古い建物はきっちり保存していこうということになり、さらに、保存するだけでなく、再利用を図っていこう。そして、その場所にあっては使い勝手が悪い場合は、大胆に動かそうということにしました。
あるエリアを計画的にやろうと思えば曳き家でかなりのことができます。
隣りや動かしたい方向に建物があれば引っ張ることはできません。そうした欠点はありますが、曳き家と曳き家を組み合わせたり、あるいはある建物を壊して、その間に曳き家をやってしまう。
ジグソーパズルではないけれども、エリアを全体的に考えていくと、曳き家という手法は有効に使えるはずだということになりました。
そして、新しく作る建物は、デザインはもちろん、素材とか大きさ、こういうものを既存の建物と調和したものにしていこう、そういうことを丁寧にやることで、ずいぶん質の高い、居心地の良い外部空間ができあがります。
居心地の良い外部空間をつくることをハード上の一番の命題にしようということになりました。
これらを進めていくには、官は官の立場があり、民は民の立場がありますから、官と民が一体となって同じ価値観でやるというのではなく、自分たちの立場で折り合いがつく部分は一緒にやっていくという考えに至りました。
どちらかがどちらかに従属しては駄目だということです。
◆行政も一当事者に
このように口で言うのは易しいです。
実は、計画して民間サイドの了解をとった後、最後に行政に持っていくと、やっぱり行政の反発に遭います。
「何だ、若造がふざけて」みたいな感じが半年ほど続きました。
説明を重ねていてくうちに、半年くらい経った後、ようやく行政は「これは乗った方が特だぞ」と考えたようです。
私たちが説いたことは二つありました。
一つは建前です。
「いまは民間の協力なんかなくたって何かできると思っているかもしれないけれど、将来、財政が傾いてきたら、いまみたいな方法はとれませんよ」と言いました。
行政は単年度主義です。
「財政がそれほど貧しくない今のうちに、財政負担をかけない開発手法を身に付けておかないと、将来、続きませんよ」と説きました。
これはお説教みたいなもので、半分面白くないわけですが、理屈で言えばまぁそうだなぁというくらいには受け止められたのではないでしょうか。
行政が心を動かしたのは二番目です。
「行政だって本当は良い物をつくりたいんでしょう」と言いました。
「行政は力があると思っているけれども、クレームに弱いでしょう。たとえば、議会が反対するとか住民が署名運動をしたら頓挫しちゃうでしょう」と。
当時、ちょうど成田空港がまだいろいろ問題を抱えていた時期でした。
「成田を見てください。国家権力でやったって、あのざまですよ」と。
どうして行政はいままで自分は力があるものと錯覚してきたか。
行政がいままでクレームなくやってこれたのは、近隣市町村もやっていることをやるからです。それをやっている限り、手続きにさえ間違いがなければ、行政の力は無敵です。
だから行政にはこう言ってきました。
「考えを変えてみてください。近隣がやって前例がある。手続きは間違いない。そういう事業に情報性はありますか?新規性はありますか?ないでしょう?つまり、新規性があることをやるということは、必ず反対がある。クレームがあるんですよ。それをどうやって突破するかです」と。
そして、「その方法はひとつあります。行政がリーダーだとかコーディネーターだとか、そういう立場は止めてみてください。行政も一当事者。コーディネーターは宮本忠長先生。地権者はイーブンの立場で多数決で決める。そうするとなんでもできますよ」と伝えました。
「たとえば議会が反対する。ところが、地権者である個人2軒と長野信金と小布施堂はやると言ってます。5分の4で押し切られます。被害者を装えば何でもできますよ。なまじ行政が何かをやろうと思うから、新しいことをやろうと思うから、抵抗があるだけなんです。これが戦後の日本のメカニズムです」と、生意気にも説いたわけです。
行政がプライドを捨て、一当事者に成り下がることによって、別にその当事者が複数いた場合に、仮に行政が反対したとしても、あるいは本当の反対じゃなくても、議会対策として反対すると、物事は進んでいってしまう。
こういうことです。
これを半年間説いて回ったら行政は乗ってくれました。
それ以後、民間サイドのイベントに、行政も一当事者として乗る。実行委員の一人として乗る。この方式により、いろんなことがやりやすくなりました。
これが後に小布施方式と言われるようになるわけです。
たいてい、「いやぁ、住民が主体で」と言っても、結局は行政が事務局をやっています。
しかし、小布施の場合は、行政がお金を出してやるイベントは、二年に一度くらい。あとは民間の企てに町が一当事者として乗る。しかもできれば事務局はやらない。ここがミソです。
信用は供与するけれども、渡すお金はないぞと、こういうイベントが多いです。
これも言ってみれば、町並み修景事業から転げ出たオマケみたいなものです。