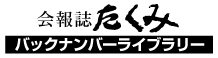![]()
平成23年度通常総会 記念講演会「歴史から学ぶ」
◆学校で習う歴史と本当の歴史との違い
その次に気がついたのは、学校で習う歴史と私たちが本当に使わなければならない歴史というものは、ちょっと違うということです。
教科書を見てください。大坂の町は秀吉が造りましたとか、三重県の津の町はなんとかとあります。これらはいずれも有力大名の拠点です。教科書はこうした城下町のことしか触れていません。
ところが、全国津々浦々、商業都市もあれば、農村部には小布施のようにちょっとした町場のような集落もある。
そういうところは大名が造ったのではなく、民間が造った。ここです。非常に重要なのは。
つまり、教科書にあるように、大名が造った軍事拠点である、あるいは商業の拠点であるような都市も確かにあります。
しかし、数の上では、自然発生的な、自然発生的と言っても、ちゃんと都市計画をつくり、区画をつくった、民間がお金をはたいた町が大部分だということです。
日本の歴史は不幸にも文献歴史で、文献に残っていないことは歴史上、存在しないことになってしまう。
しかし、現実には、小布施の町は存在しています。17世紀、1600年代には、小布施の中でも現在の大字小布施といわれているところは市場町として、商業都市として新たに造成してできているわけです。
大名は一銭もお金を出していない。にもかかわらず、なかなか工夫に満ちています。こんなことが全国津々浦々でやられている。
日本というのは、欧米に比べ、市民社会の歴史が特に長い。こんな国はありません。
ヨーロッパの市民社会は、一番古いイギリスでも、産業革命以後の200年か250年の歴史しかないのに対して、日本の場合は土地の私有が実的に認められて営々と町も造られてきた。
こういう歴史が700年前から、鎌倉時代から始まっているわけです。
世界の三大料理、フランス料理、中国料理、それとトルコ料理。いずれもその社会がつくったというよりは宮廷料理です。王侯が開発した食文化です。
それに対して日本の世界に誇るべきは、一般の人間が洗練させて世界に普及させた寿司や天ぷら、すき焼きもそうです。一般の人が開発した料理が世界を席巻しています。
そして、何より誇らしいのは、宮廷料理というものもあるのかもしれませんが、そういうものは世界に輸出したりしません。
日本人というのは市民社会の歴史が長いだけあって本当によく工夫しています。
◆水路に見られる知恵
小布施の町で宅地の区画割りをするとき、扇状地ですから傾斜地で、基礎工事が結構、難しい。特に感心するのは、十四ヶ郷用水という用水の存在です。
扇状地の一番上の、水上というところから網の目のように来ていますが、その用水は、地面の傾斜よりも緩やかに作られています。
そのため、ある部分まで来ると、地面と水路の傾斜の差が大きくなって、そこで水路を滝のようにストンと落としている。
水路の何メートルか置きに、非常に深いところがあるのですが、これが実は大雨が降ったときの遊水池になっているという仕掛けです。
ですから、普段、町を歩いていると、落差があるところは水の音がするわけです。
何も音を楽しむだけではなく、雨が降ったときにこの深い部分に水を貯める。もちろん底はなくて、地下浸透がメインです。さらに、水路の途中の高いところに池のようなものをつくっている。これも遊水池です。あふれてきたら、そこに水が入る。
こういう仕掛けだらけです。
しかし、残念ながら戦後の土木工事というものは、都市と同じ傾斜で水路を造ってしまった。
遊水池らしいものはないし、地下浸透しないようにU字溝にしてしまいます。
その結果、どうなるかというと、夕立のたびにどこかがあふれる。
最近のように、雨がゲリラ豪雨化してきていますから、これは小布施のような小さな町から、長野や松本のような大きい町でも共通した問題でしょう。
東京などは手を焼いて、巨大な地下のピットのようなものを造ったり、いろいろやっています。小布施の例のように、昔は斜面と同じ斜度で水路をつくるなんてことはせず、ちゃんと斜度を変えて造っていた。土木系の方々はそういうところを見てほしい。
そういう感じがするわけです。