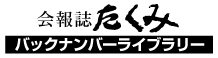![]()
平成23年度通常総会 記念講演会「歴史から学ぶ」
◆公と私
それからもう一つ、非常に尊いのは、その用水が各家庭の敷地を貫いていることです。
水をきれいに流そうという「公」意識を誰もが持っていることです。
しかし、一方においては、自分の敷地内の護岸は思い通りに使っている。あるお宅は洗い場を作ったり、中水道的な使い方をする用水もありますので、それを池にしてみたり、池にするといっても、一旦、満杯になるとオーバーフロウしますから、水を堰き止めるわけではない。
したがって、その公と私というのを上手く調和させ、私という部分にはある程度の自由を認めています。
考えてみると、錦絵や挿絵などでお気づきの通りですが、西南戦争というのがありました。
西南戦争の良し悪しは別として、政府軍というのはお仕着せの軍服を着ています。
それに対して、鹿児島の私学校軍というのは西郷隆盛以下、だいたい黒っぽい袴に白っぽい上着、着物です。白虎隊もそうでしょう。
袴は同じ袴かというと、黒っぽいというだけで、それぞれ違う縞模様だったり、色だったり、上も白っぽいとうだけで、若干模様の違いなんかもあるでしょう。
つまり、日本の考える伝統的な公というのは方々に出てくるのです。
しかし、細部に至っては、あるいはその場所によっては個人の自由である。自由でいいという、この自由と統制部分とが上手く調和しているのが、多分、日本なのだろうと思うわけです。
ところが、これを打ち破ってしまったのが、明治20年頃。日本の官僚制度を作った山縣有朋です。その10年前まで生きていた大久保利通が作っていたら違う官僚制度になっていたと思うわけですが、山縣は何をやったかというと、日本のそういう歴史を全然見ずに、公というものを一手にお上に委ねてしまった。
これが明治22年に出来た市町村制度であり、23年に開設された明治時代の国会です。
いまのように行き詰まった時代では、もう一度、明治元年から明治20年くらいまでの太政官政府時代。明治時代というよりも、太政官政府時代をおさらいすることで、いろいろなヒントがあるのではないか、そういう気がするわけです。
先の地震で、久しく聞いていない地名を再び聞くことになりましたけれども、宮城県の野蒜というところは、大久保利通が港を造ろうとして、いまも跡が残っているそうです。
そこから船でサンフランシスコへ行こうとすると、横浜から行くよりも2日短くて済む。
野蒜から出れば、当時の船でサンフランシスコまでだいたい11日。横浜からだと13日かかる。
そこで、大久保利通は港を造ろうとしたけれども、外の波を防ぐ防波堤が、当時の技術ではどうしてもできなかった。それで、断念したという地でありました。
それが今回の地震で再び野蒜という地名を聞くことになりました。
◆公の道
江戸時代の都市開発は、ある勧進元が開発費用を負担して、入居者がその土地を買うか借りるかして入ってきて最終的な負担者になる。多分、そういう形で進めていったのだと思うのですが、これは、いまPFIと言っておりますけど、江戸時代はこうしたPFIが一般的でした。
PFIは何も目新しいことではなく、それが日本の本来ではないかというような気がします。
そして、何より賢く、頭が良いと思うのは、その赤線ないし馬入れ、あるいは水路。そういうものを誰の物ということでなく、共有の物だと考えることです。
ですから、建物を見ると、だいたい庇の下には水路が流れていて、雨だれがその水路に落ちるように造られています。
明治になると、赤道とか水路を、一応、大蔵省の土地ということに、便宜的にしました。
その結果、どうなったかというと、いまの建築基準法のせいでしょうか。庇が水路に出ていると、下にあるのが大蔵省の持ち分であれば、違法建築ということになってしまいます。この建物を修理するとなるとセットバックしなくてはいけない。
「水路に落ちるようにつくったものを、なぜセットバックする必要があるのか」と言いたくなるくらい、おかしなことになってしまいました。
大蔵省では7~8年前、この馬入れ道を、一般の国民がほとんど知らないうちに市町村に払い下げてしまいました。これは非常に残念なことです。
一方、小布施のように、民間が不法占拠しないうちにきっちりと遊歩道にしようと燃えている市町村は良いのですが、たいていの市町村、特に都市部は不法占拠されたまま。ズタズタというところが多いと思います。
ところが、イギリスはやっぱり頭が良い。
1920年代、この日本の馬入れ道みたいなものをどう考えるか大議論がありました。
その結果、フットパスという素晴らしいシステムができ上がりました。極端なことを言えば、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドと、イギリス国中がそのフットパスと言われる歩く道でつながっています。
本屋に行けば、フットパス専用の地図も売っています。
イギリスの首相の別荘は5カ所あります。一人で使いきれないから、たいてい、歴代の首相は1カ所か2カ所使うのですが、サッチャー元首相のお気に入りの別荘というのが田舎にありました。
菅平牧場みたいなところで、フェンスがあって、一見、豪華な建物が1つ建っているだけです。その建物が総理大臣の別荘です。その別荘の前庭を横切るようにフットパスが走っています。
総理大臣の別荘であろうと、フェンスのところにある木戸を自分で閉めて、庭を横切って、向こうの木戸をまたきちんと閉めさえすれば、誰でも通っていいというように機能しているわけです。
フットパスはいくつかの種類があり、馬と人間は良いけど、自転車は駄目とか、ここからここまでは自転車や馬や人が歩いていいとか、いろいろなルールがあります。そしてまた、フットパスを歩くときの心得みたいな、そういうものもきっちりしています。
日本は赤道とか昔の人が考えた共有のものを、いったん、国に召し上げた。そうして国は自分たちにその処理能力がないものだから、また市町村に払い下げた。そんな馬鹿なことばかりやっているのが日本国政府で、残念だなと思うわけです。