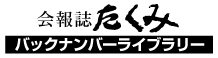![]()
平成23年度通常総会 記念講演会「歴史から学ぶ」
◆日本も訴訟社会だった
それに比べると、江戸時代または明治20年までの日本社会というのは、非常に成熟化していました。
面白いのは、小布施の例ですが、小布施の町場をつくった久保田家という勧進元がいます。
これが1700年代になっても、元々勧進元の子孫だからということで、実は小布施の町は、商店、でその前に市が建っています。
その市で商売をする人と、そこの後ろの商店の持ち主は別人です。多分、賃借料を取ります。
その勧進元のところは角にあるものですから、L字型に二面にわたって場所を貸してくれとなるわけで、「それはけしからんじゃないか」と訴える者が出てくる。
ほかのうちはみんな自分のうちの間口だけ貸しているのに、元々小布施の町場を拓いた人間だけが二つの通りに面していて、両面を貸しているのは不当だと訴えを起こしています。
しかし、その勧進元の方は「そうは言うけど、俺のうちの先祖がこの町場を拓いたんだから、この特権は許せ」みたいなことがちゃんと訴訟になっているのです。
アメリカの社会を指して日本人は訴訟社会だと言いますが、江戸時代も、いまのアメリカほどかどうかは知りませんが、結構、訴訟だらけです。
ただ、そんなに殺伐としたものではなく、ちょっとあいつ儲けすぎだと思うと、軽く訴えるといった感じです。
江戸時代、大きい町には公事方宿というものがあって、単に泊めるだけではなく、「あんた訴訟に来たのか?何?江戸町奉行に訴訟する?」と聞くと、「今月は止めとけよ、鳥居耀蔵が当番だから、北町の当番だから、来月になると南町奉行所の管轄になるから、訴えるなら来月の方がいい」とか教えてくれました。
ちゃんと奉行所間に競争原理が働いていて、そういうアドバイスをするのが公事方宿でした。
小布施の町を拓いた勧進元が、数代、代を経ても、他の人間より権利を持っているのはけしからんと、そういうようなことが訴訟になるような社会でした。
考えてみれば、面白い社会でもあったわけです。
◆日本人の空間感覚
江戸時代には優れたものがいくつかありましたが、空間の演出もかなり上手いと思います。
城下町に行くと、観光ガイドさんが、「ここは城下町だから、敵の目をくらますためにクランクがあったり、行き止まりがあったりします」と、こういう説明をします。
しかし、あれは個人的には疑問です。本当の理由は違うのではないかと思っています。
その証拠に、クランクは宿場にもあるし、城下町ではなくともあるのです。
着目したいのはクランクの長さです。だいたい600mです。多少前後しますけど、決して800m以上のものはないし、500m以下のものもない。
ということは、600mくらいでクランクをつくることが、一つのご町内としてちょうどいい戸数だと捉えられているのではないか。町内が変わるところは空間を区切った方がいいと、それが大きなクランクやT字の目的だろうと踏んでいます。
また、お城の枡形は、敵に対して味方が攻めていくときに、枡形に入る人間がおおむねどのくらい必要か分かるからと教えられ、ひとかたまりになったら出撃するとか、もっともらしい理由を付けて説明されてきましたが、村の辻みたいな場所を見ると、小布施でも須坂でも、長野でもどこでもいいのですが、一本の道路が延びてきて、もう一本の道路が延びてくる。この二本の道路がそれぞれ伸びてきてつながる。これがだいたい村の辻です。考えてみると、これも枡形です。
村の辻までそんな防衛上のことを考えてつくったのでしょうか。そうは思えないので、やっぱり日本人の空間感覚なのだろうと考えるのが一番納得しやすいことだと踏んでいるのです。
さらに、街路樹です。
たとえば、杉や松、こういう一種類の樹種を街路樹として植えるのは、江戸時代までの作法では、町と町の間の郊外、街道筋、それから町の中でいえば、お寺やお宮に至る参道、これらについては一種類の木を植えています。
例外的なところでは、水辺には柳を植える。一つの種類を植えているのはこの三つですけれども、どうやらそれ以外は勝手にいろいろな木を植えていた。これがやっぱり江戸時代までの日本人の植栽に対する作法ではないかと思います。
町並み修景をやるときに、私たちはできるだけ古い明治とか大正時代の小布施の町の写真を集めました。それらを一つの根拠、出発点にして、デザインをしていきましたから、都市計画に従ってやると、いまの並木のように一種類の木を植えていってしまいますが、一種類の木しか植えないのは参道か街道筋、それから水辺の柳。それだけであって、他は違うのではないかというのが私たちの仮の結論です。
そして、言うまでもなく道。道というのは、何か通過するための場所だけではなくて、道そのものが広場の機能を果たしている。
道ではないですが、小布施の場合は「はよんば」という、これはかなり珍しいことだと思いますが、江戸時代から広場を持っています。こういう歴史も大事にしていこうと思うわけです。
そして、用水。小布施の場合は一つの敷地がウナギの寝床みたいに縦長で、表通りに面した自分の家との境に一本、用水が通っています。
それから表の通りに近い、3分の1から4分の1くらいのところにもう一本、通っています。これが実は一番重要な生活用水。中水道です。
そして、裏にもう一本、通っています。裏にある前栽畑のための灌漑用水。ですから、用水といっても、一つの敷地に表部分、表に近い敷地内の部分、そして一番裏と、三本走っている。
そして、それぞれ用途が違うということです。
表から順に言うと、道路に水を撒いたり、砂埃を除けるために水を撒いたりという道路の管理やあるいは防火。そういうものが表の用水。表に近い住居部分に近いところを流れているのが中水道用の生活用水。そして一番裏が前栽畑の灌漑、作物のための水です。